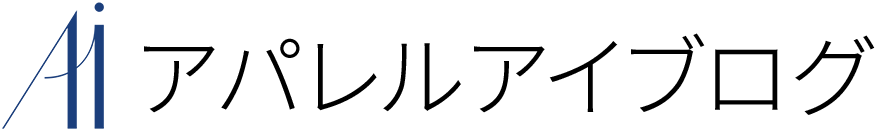営業部の福永浩士です。
前回の【エリア編】につづく第二弾、【歴史編】をお届けいたします。
備後の中でも、特に福山を中心とした歴史についてお話しします。
目次
- 綿花の栽培
- 備後絣
- 縫製技術の向上
- まとめ
綿花の栽培
福山の繊維の歴史は江戸時代に始まりました。
福山藩の初代藩主、水野勝成(1564-1651)が綿栽培と絹栽培を奨励したそうです。
婦女子の副業として綿織物が織られ、福山城下の問屋や市場で売らせたことから織物業が盛んになりました。
備後絣の発展
1790年に幕府から倹約政策が実施され、絹織物の着用が禁止になったことから、綿織物が発展していきました。
綿織物の研究が進み、その流れで考案されたのが「備後絣」で、備後絣は久留米絣・伊予絣と並び「日本三大絣」と称されました。
備後絣は全国的に有名になり、明治には年産11万反以上、1930年頃には100万反を突破しました。
備後絣の発展から時代を経てレディースパンツへ、また藍染めの技術はデニム染色等デニム生地の発展にも繋がり、現在の各繊維産業を形成しています。
縫製技術
増産・効率化を背景に、機械化が進みます。ミシンが導入され、パンツやモモヒキなどの縫製も始まりました。
戦時中、縫製工場は軍の統制下に置かれ、軍服の縫製を命じられます。軍服は厳格化された規格品のため、そこで縫製技術が向上しました。
そういった技術がアパレルの各分野に活かされ、中でもワーキングウェアの発展は素晴らしく、現在でも備後地方が全国のトップシェアを占めています。
まとめ
綿花栽培から備後絣、縫製技術と簡単に歴史をまとめてみました。
エリアや技術などの特性を活かし、デニム・婦人ボトム・ワーキングウェアなど、いろんな形で現在に至ってます。
糸・生地を生産するところから、製品を販売するまでいろんな企業がありますが、特に「川中」と言われる企業が多いのも備後の特徴です。
次回は【企業編】という形でお届けしようと思います。